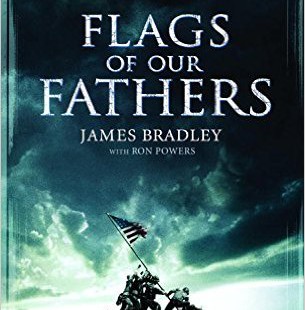
アーリントン国立墓地とフィリピン(3)ウィリアム・ハワード・タフト
William Howard Taft (1857-1930), Section 30
アーリントン国立墓地とフィリピン・マップ(ゆかりのアメリカ人たちの墓碑を赤いピンで、フィリピーノたちの墓碑を青いピンで表示しています)。 (目次に戻る)
1901年3月、フィリピン独立革命政府指導者のエミリオ・アギナルドが、ルソン島東部イサベラ州のパラナンに潜伏中のところを、フレデリック・ファンストン准将により逮捕されます。米本国でも1901年9月6日、マッキンレー大統領が暗殺され、セオドア・ローズヴェルト副大統領が大統領に昇格するという全米を震撼させる大事件が発生しますが、アギナルドの逮捕・投降(このあとアギナルドは米国への忠誠を誓います)は、各地の革命軍を投降へと向かわせていきます。
自伝『グッド・ファイト』によれば、当時、革命軍少佐としてバタアン半島で戦っていたマヌエル・ケソン(Tour-1)も、最初は逮捕の報を信じませんでした。しかし、上官の命で真偽を確かめるため単身で米軍に投降したケソンは、マラカニアン宮殿で虜囚の身となっていたアギナルドに直接面会して、力なく忠誠宣誓の事実を語るアギナルドを目の当たりにして絶望し、上官に事実を報告して任務を果たすと戦線を離脱しました。この時期はまだ、投降者は原則として無条件に恩赦されていたのでケソンもすぐに学業に戻るつもりでいましたが、理由も告げられず訴追されることもなく4ヶ月間にわたって劣悪な環境の拘置所に収監されました。晩年の自伝でケソンはこの経験でいっそう反米意識を募らしたと回想しています[i]。
 このように軍事的制圧が進む一方で、「平定」の方法論をめぐって米軍と政府の間で深刻な摩擦が生じます。アーサー・マッカーサー軍政総督(Tour-2)とフィリピン委員会Philippine Commission委員長ウィリアム・ハワード・タフトの対立です。1900年4月、軍政から文民統治への移行を視野に入れて、立法権限をもったフィリピン統治の最高評議機関としてフィリピン委員会が発足します。サンフランシスコを出発した委員会は太平洋航路で準備会合を重ね、6月にフィリピンに到着すると、9月以降、立法権限を行使してフィリピンの法制度を着々と整備していった。この過程で、文民統治への移行を急ぐタフト委員長と、軍事作戦への政治の介入を嫌うマッカーサーの意見の食い違いは感情的対立にまで発展します。結局、権力闘争はセオドア・ローズベルトの信任が厚いタフトの勝利におわり、1901年7月、タフトは初代文民総督に任命され、マッカーサーは事実上の更迭人事でフィリピンを去ります。このとき、すでに軍人の道を歩み始めていた息子ダグラスに父の敗北は大きな影響を与え、文民統制に対する強い不信感を植えつけたと言われています。一方タフトは、総督(1901年~04年)、陸軍長官(1904~09年)をへて大統領(1909~13年)にまで登り詰めてゆくことになります。
このように軍事的制圧が進む一方で、「平定」の方法論をめぐって米軍と政府の間で深刻な摩擦が生じます。アーサー・マッカーサー軍政総督(Tour-2)とフィリピン委員会Philippine Commission委員長ウィリアム・ハワード・タフトの対立です。1900年4月、軍政から文民統治への移行を視野に入れて、立法権限をもったフィリピン統治の最高評議機関としてフィリピン委員会が発足します。サンフランシスコを出発した委員会は太平洋航路で準備会合を重ね、6月にフィリピンに到着すると、9月以降、立法権限を行使してフィリピンの法制度を着々と整備していった。この過程で、文民統治への移行を急ぐタフト委員長と、軍事作戦への政治の介入を嫌うマッカーサーの意見の食い違いは感情的対立にまで発展します。結局、権力闘争はセオドア・ローズベルトの信任が厚いタフトの勝利におわり、1901年7月、タフトは初代文民総督に任命され、マッカーサーは事実上の更迭人事でフィリピンを去ります。このとき、すでに軍人の道を歩み始めていた息子ダグラスに父の敗北は大きな影響を与え、文民統制に対する強い不信感を植えつけたと言われています。一方タフトは、総督(1901年~04年)、陸軍長官(1904~09年)をへて大統領(1909~13年)にまで登り詰めてゆくことになります。
 1930年に亡くなったタフトは、アーリントン国立墓地に葬られた最初の――そしてジョン・F・ケネディと共に今のところふたりだけの――大統領となりました。墓石は高さ4メートルあまりの花崗岩で出来たギリシア風の石柱で、墓苑正面入口のメモリアル・ゲートに近い30区画にあります。タフトはローズベルトの後継指名により大統領に選出されながら――革新主義Progressivismをめぐる共和党内の亀裂から――四年後には革新党Progressive Partyを結党して出馬したローズベルトと分裂選挙となり、民主党ウッドロー・ウィルソンに政権を奪われました。このため大統領としてよりも、むしろその後に合衆国最高裁長官(1921~30年)として本領を発揮したと言われます。しかし、ことフィリピン政策については――文字通りのペット・プロジェクトとして主導し続け――決定的な役割を果たしました。タフトの総督就任から大統領退任まで(1901~13年)は、フィリピン史における「タフト時代Taft Era」として知られています。アメリカ人ゆかりの街路名が独立後次々と改名されたなかで、マニラ都心の大通りが今でも「タフト・アベニュー」と呼ばれていることは、フィリピン史における彼の存在の大きさを物語っています。
1930年に亡くなったタフトは、アーリントン国立墓地に葬られた最初の――そしてジョン・F・ケネディと共に今のところふたりだけの――大統領となりました。墓石は高さ4メートルあまりの花崗岩で出来たギリシア風の石柱で、墓苑正面入口のメモリアル・ゲートに近い30区画にあります。タフトはローズベルトの後継指名により大統領に選出されながら――革新主義Progressivismをめぐる共和党内の亀裂から――四年後には革新党Progressive Partyを結党して出馬したローズベルトと分裂選挙となり、民主党ウッドロー・ウィルソンに政権を奪われました。このため大統領としてよりも、むしろその後に合衆国最高裁長官(1921~30年)として本領を発揮したと言われます。しかし、ことフィリピン政策については――文字通りのペット・プロジェクトとして主導し続け――決定的な役割を果たしました。タフトの総督就任から大統領退任まで(1901~13年)は、フィリピン史における「タフト時代Taft Era」として知られています。アメリカ人ゆかりの街路名が独立後次々と改名されたなかで、マニラ都心の大通りが今でも「タフト・アベニュー」と呼ばれていることは、フィリピン史における彼の存在の大きさを物語っています。
フィリピン、タフトと来れば、日本で知られているのは、日本の朝鮮半島に対する宗主権とアメリカのフィリピンに対する主権を相互に承認しあった秘密協定、いわゆる「桂・タフト協定」でしょう。日露戦争・日本海海戦(1905年5月27日)で圧勝したとはいえ国力を使い果たしていた日本が講和の斡旋をローズベルトに依頼してポーツマス講和会議が始まるのが同年8月、翌9月5日に講和条約が調印されていきます。「協定」が「結ばれた」のは、この直前です。フィリピン総督の仕事を離れて1904年2月に陸軍長官に就任したタフトは、ローズベルト大統領の特使としてアジア歴訪の旅に出て、1905年7月27日、東京で桂太郎首相と会談しました。
この会談の冒頭で、タフトは日露戦争における日本の勝利を「フィリピン諸島方面への日本の侵攻の確実な序曲」だとする「一部親露派」の見方を示し、フィリピンがアメリカのような日本の友好国によって統治され、「いまだ自治に適していない現地人たちの誤った統治」や「非友好的なヨーロッパの国の手中」に落ちないことこそが日本の利益だと述べます。桂は全面的に賛同して日本のフィリピンに対する「攻撃的意図」を完全に否定します。さらに桂は日米英三カ国間で極東問題での「了解」・「同盟」が必要だとして、韓国に関しては「戦争の論理的帰結として半島問題の完全なる解決」が必要だと述べます。これに応じてタフトは「韓国が日本の同意なしには外国と立約しえない」という程度にまでの「日本国による韓国に対する宗主権の樹立」は「現戦争の論理的帰結であり、東洋における恒久的平和に直接寄与する」と発言しました[ii]。
日本の韓国保護国化とアメリカのフィリピン支配の相互承認が会談の骨子でした。同じ頃、保護国化の危機に対して韓国の高宗は、1882年修好条約の「周旋条項」に基づく介入を要請しましたが、ローズベルト政権は一切応じませんでした。そして第2次日英同盟(8月12日)でイギリスから、ポーツマス条約(9月5日)でロシアから韓国における優越権を認められた日本は、第2次日韓協約(11月17日)により韓国を保護国化していきます。
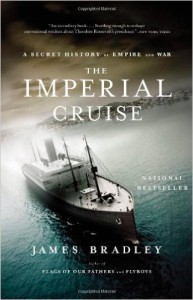 『硫黄島の星条旗Flags of Our Fathers』で知られる作家ジェイムズ・ブラッドレーはImperial Cruiseという興味深い作品でこの「協定」に焦点をあて、セオドア・ローズベルトTheodore Rooseveltのアジア外交を激しく批判しています。もしもローズベルトが──アメリカ合衆国(以下、アメリカ)のフィリピン支配と日本の韓国保護国化を相互に認める──韓国を切り捨てた日本贔屓のアジア外交をしなければ、日本の膨脹主義にも歯止めがかかり、「私の父も第2次世界大戦の太平洋での戦いで傷つかないですんだかもしれない」というのが、ブラッドレーの言い分です(p.331)。歴史解釈としては飛躍がありますが、フィリピン征服を通じて19/20世紀転換期にアメリカが東アジア国際政治の舞台に参入したことの意味の重さを考えさせる問いです。そして日本ではあまり知られていないことですが、この「協定」の一方の当事者であったタフトが、フィリピンの「平定」に対する強い関心から取り組んでいたことも注目すべきでしょう。
『硫黄島の星条旗Flags of Our Fathers』で知られる作家ジェイムズ・ブラッドレーはImperial Cruiseという興味深い作品でこの「協定」に焦点をあて、セオドア・ローズベルトTheodore Rooseveltのアジア外交を激しく批判しています。もしもローズベルトが──アメリカ合衆国(以下、アメリカ)のフィリピン支配と日本の韓国保護国化を相互に認める──韓国を切り捨てた日本贔屓のアジア外交をしなければ、日本の膨脹主義にも歯止めがかかり、「私の父も第2次世界大戦の太平洋での戦いで傷つかないですんだかもしれない」というのが、ブラッドレーの言い分です(p.331)。歴史解釈としては飛躍がありますが、フィリピン征服を通じて19/20世紀転換期にアメリカが東アジア国際政治の舞台に参入したことの意味の重さを考えさせる問いです。そして日本ではあまり知られていないことですが、この「協定」の一方の当事者であったタフトが、フィリピンの「平定」に対する強い関心から取り組んでいたことも注目すべきでしょう。
1909年10月、伊藤博文が安重根に殺害されたとき、『ニューヨーク・タイムズ』紙は、その数日後の社説で伊藤の韓国政策とタフト総督当時のフィリピン政策の共通性を指摘しています。そして、「日本の韓国政策が物質的福祉の向上をめざしているのはフィリピンにおける我が国と同じ」であり、「伊藤公の精神が実行に移されれば、長期的には朝鮮人は、弱体な王政のもとでは得られなかった豊かさと近代文明の諸思想を得られることになるだろう」と韓国併合に向かう日本を完全に支持したのでした[iii]。
この後、くわしくは『東アジア近現代通史第2巻』所収の小論をご覧下さい。
[i] Quezon. The Good Fight, 74-80.
[ii] 長田彰文『セオドア・ルーズベルトと韓国』未來社、1992年、102-106頁。
[iii] New York Times, October 31, 1909, p.8.


Recent Comments