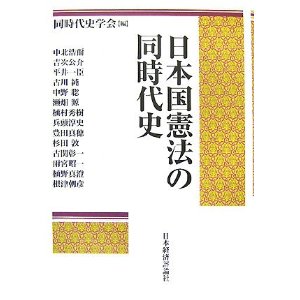
日本国憲法のクリティカル・スタディーズ
前安倍内閣期と重なる2006年12月、同時代史学会は「同時代史としての憲法」をテーマとして大会を開催しました。
http://www.geocities.jp/doujidaisigakkai/annual_meetings/2006.html
このとき前半の司会として参加したときの感想を記した文章です(同時代史学会編『日本国憲法の同時代史』日本経済評論社、2007年、77−87頁)。そのまま再録します。ここで参照している報告は、すべて『日本国憲法の同時代史』に収められています。どうぞ是非お読みになって下さい。

日本国憲法のクリティカル・スタディーズ
中野 聡
自民党の憲法改正プロジェクトチームが発表した「論点整理(1)」がめざすような「改憲 」に対しては明らかに「護憲」(2)に与する研究者・市民が集う場と言ってよい同時代史学会が主催した2006年度大会企画「同時代史としての憲法」は、しかし、結果として――現行日本国憲法の改正に一切手をつけるべきではないという意味でのカッコなしの――護憲の論理が、自民党・民主党内の復古主義や「ふつうの国」主義の側からだけでなく、国民国家論・ジェンダー論・福祉国家論や近代憲法批判など、多様な立場からのクリティカル・スタディーズ(批判的批評研究)の対象とならざるを得ない現状を示す舞台となった。こうした日本国憲法批判は、場合によっては改憲の要求につながり得るし、民主党の「創憲 」(3)や公明党の「加憲 」(4)とも相通じる立場となり得る。こうした議論は「改憲」派に足下をすくわれるので大変に危険であると護憲派は述べるであろう。はたしてこの問題をどう考えたらよいのか。このような問いを念頭におきつつ、全くの門外漢・一聴衆の立場から、第1部・第2部の各報告をめぐる雑駁な感想を述べてみたい。なお筆者は第1部の司会であったが、午前・午後の各報告の論点は密接に相関していた。そこで誠に勝手ながら第1部・第2部両セッションの報告に言及させていただきたい。
(1) 憲法9条のクリティカル・スタディーズ
第1部・吉次公介氏の報告は、憲法9条が「ビンの蓋」の役割を果たしつつ、日米安保条約・沖縄に偏在する米軍基地・日本の再軍備(自衛隊の軍備拡張)と共存し、さらにはそれらと相補的な役割さえ果たしてきた側面を指摘することによって、戦後日米関係・東アジア国際関係史のリアリズムの視点から憲法9条をクリティカル・スタディーズの俎上に載せるものだった。もしも憲法9条がなかったならば、日本の再軍備や日米軍事協力の拡大がアメリカ・東アジアの周辺諸国・日本人自身によってここまで容認されることはなかったかもしれない。このような見方が可能なのだとすれば、自民党・保守勢力による度々の「改憲」攻勢に対して憲法9条を守り抜いてきた護憲派は、不本意にも日本の軍拡と日米安保体制の強化に貢献してきたことにさえなってしまう。もちろん護憲派は、憲法9条と現実の落差を9条の側から非難告発する人々である。また、本会会員の渡辺治氏は、吉次氏とは逆に9条と平和運動が日本の保守政治を厳しく制約して軍事大国化や核の容認を阻んできた側面を重視する議論を展開している(5)。同じ問題をどちらから見るのかということなのであろうが、各種世論調査で依然として「圧倒的」多数派の日本人が、9条改憲には否定的な一方、防衛費世界第3位の自衛隊を合憲とすべきだと認め 、日米安保体制を評価している現実をふまえれば(6)、9条と軍事化の共存について護憲派もまた責任と回答を迫られていることを意味している。
憲法9条を戦後思想の問題としてクリティカル・スタディーズの俎上に載せた第2部・植村秀樹氏の報告は、戦後の護憲運動を支えてきた体験的平和主義の限界を鋭く批判するものだった。戦後民主主義の代表的知識人である丸山真男において、その反軍思想と平和主義、民主主義と市民社会の構想が、徹頭徹尾、自らの軍隊体験や被爆体験に根ざした一貫性をもつ一方で、戦争体験を普遍的思想に昇華するという点では貧弱さを免れなかったと指摘する植村氏は、そのような体験的平和主義はしょせん風化を免れないのであって、単なる戦争体験の継承を超えた平和主義の普遍思想化・制度化がなければ、戦争のない時代としての「戦後」は確実に終わってゆくだろうと警告する。
安易な比較は慎むべきだとは思うが、やはりドイツのことが頭に浮かんでしまう。たとえばトーマス・マンが、第2次世界大戦中、亡命先のアメリカで綴った小説『ファウスト博士』は、ナチズムそのものについてはほとんど語らずに、ニーチェをモデルにしたと思われる架空の音楽家の生涯に託して、ドイツ文化に無限の郷愁を寄せながら、ドイツ的なものに対する絶望と決別の書となっている。これも、体験を思想に昇華する作業のひとつと見てよいだろう(7)。ファシズムの復古を制度的に封印し、時効のない戦争犯罪を追及するヨーロッパ諸国の法制度も、このような体験の思想化に裏付けられて初めて内実を伴って維持され得るものなのだろう。このような思想的営為が日本人の場合、欠けていたのだろうか。あるいは、そのような営みがあったのに、我々はそれを見逃しているだけなのだろうか。
両氏の報告は9条護憲論があえて「見ようとしないできた」側面に光を当てたものだ。それでは憲法9条の護憲をめぐる真に誠実な立場とは、いったい何であろうか。体験を思想と制度に昇華させ、終わらない「戦後」を実現させるために必要なのは、はたして9条を死守することであろうか。「改憲」攻勢への対抗という政治的課題を考えれば、それ以外に可能な現実政治的選択肢はないようにも思われる。しかしそれは同時に、沖縄に犠牲を強いる現実を放置して安保・自衛隊と9条の「解釈と運用」による共存がいちばん快適だと考えてきた――読売新聞世論調査で32.6パーセントに達する(8)――言わば「いい加減な平和主義」の多数派を、改憲阻止の政治目的に動員して協調しなければならないことを意味している。9条改憲阻止がこのような枠組みの中にとどまる限り、両氏が鋭く指摘した憲法9条と戦後平和主義の陥穽を克服することは、ますます遠い課題となってしまうかもしれない。
(2) 境界論から問い直す日本国憲法
憲法9条問題をめぐる吉次・植村両氏の報告に対して、第1部・平井一臣氏の報告と古川純氏による補足報告的性格をもったコメント、そして第2部の兵頭淳史氏と豊田真穂氏の報告は、それぞれ異なる主題・視点で議論を展開しつつ、いずれも憲法9条とならぶもうひとつの問題群、すなわち日本国憲法が創出し想定してきた市民像・国民像(法主体)を境界論的な視点から問い直す一連のクリティカル・スタディーズとして位置づけることができるものだった。
平井氏の報告は、南朝鮮(韓国)における国家形成が済州道の犠牲(1948年4.3事件など)のうえに成立し、日本の戦後民主主義が沖縄の犠牲のうえに成立したこと、1946年に「本土」・鹿児島県から行政分離されて米軍政下におかれた奄美において共和制憲法が構想されていたことなど、国民国家の基本法としての憲法の形成史に、地理的境界論の視点を組み入れる観点の重要性を示唆するものだった。
ここで私がとくに気になったのは、南朝鮮(韓国)を超えた朝鮮族(コリアン)の戦後という問題である。済州道が南側の反共国家に暴力的に統合された悲劇は、それ単独にとらえられるものではもちろんなく、1945年から約10年間に、朝鮮族が南北朝鮮、中国、ソ連という4つの国家に暴力的に分断され、また一方で日本やアメリカ合衆国などにディアスポラを形成するに到った全体のなかで展望する議論が必要だろう。憲法という点から言えば、朝鮮族は、4つの異なる国民国家の憲法体系に国民として分属し、さらに海外居住国の憲法体系に排除ないし包摂されてディアスポラを形成する「戦後」を生きることになったわけである。私たちはこのように断片化させられた存在としてのコリアンを想像することが、はたしてどれだけできているだろうか。
この問いに深く関連するのが第1部の古川氏のコメントであった。憲法学を「辺境」の立場から問い直す、同氏のこれまでの考究の見取り図を示したこの補足報告で、古川氏は、日本国憲法草案から「国籍による差別禁止」の条項が削除された経緯、日本国憲法第3章(国民の権利および義務)における権利・義務の主体が英文草案ではpeopleとされていたものが「国民」と訳され、さらに10条で「日本国民たる用件は、法律でこれを定める」とされた経緯、その結果として旧「外地人」すなわち台湾人・朝鮮人が、戦前は「内地」で行使できた選挙権を喪失し、さらに日本国籍を一方的に喪失させられた経緯を示した。いずれも戦後日本が国民の境界から排除した旧「外地人」の問題を鋭く提起するものである。平井氏が提起した地理的境界論を、属人的な国民の境界論から捉えなおした議論として見ることもできるだろう。
ここで私が気になったのは、外国人の権利主体性をめぐる問題であった。以前は日本国憲法が権利主体を国民と明記していた点が重視され、外国人の権利主体性を否定する学説・判例が有力だったが、1978年のマクリーン事件最高裁判決など以降、憲法によって保障された権利の性質を検討したうえで、外国人にも可能な限り保証を及ぼそうとする「権利性質」説が凡例・通説となったという(9)。とはいえ、外国人差別が憲法で明示的に禁止されなかったことに加えて権利主体が国民と明記されたことは、今日でも依然として重要な意味をもっているように思われる。「権利性質」説は、どのような権利が外国人に保障されるかについてのマニピュレーション(操作)を行政と司法に託している見解だからだ。私などは、日本社会に横行する外国人差別の現実を前にすると、最高裁判所の凡例や憲法学の通説は、はたしてどの程度、信頼されるべきものなのかと思ってしまうのである。
兵頭氏の報告は、憲法25条の生存権原理を基礎として「最低生活保障」――貧困層の利害――に関心を集中させてきた戦後日本の社会政策学が、所得比例年金の公的維持など中間層の利害関心を等閑視してきたことを批判して、新自由主義的改革の攻勢に耐え得る新たな「福祉国家」に多様な社会階層(すなわち広範な中間層)の支持を獲得できるような社会政策学の新たな展開の必要性を訴えるものだった。
この報告を聞いて私が思ったのは、「戦後」の日本社会を長く規定する存在として想像されてきた最大の社会階層である中間層が、焼け跡から生まれた日本国憲法の制定時には、まだ具体的存在として想定されていなかったのだろうということである。その時点では高度経済成長後を見渡すような展望・予想は、たしかに不可能であっただろう。このように制定時には想定されていなかった問題に対応するひとつの手段が憲法の発展的解釈とされる。たとえば、25条の「健康で文化的な最低限度の生活」保障の論理(とくに文化的という文言)を発展的に解釈すれば、中間層の利害関心にも応えられるのではないかという議論がそれにあたるだろう。しかし、文言上「最低限」の生活保障を国に義務づけているに過ぎない25条の条文そのものから、たとえば所得比例年金の公的維持に対する新自由主義改革の攻勢をはねのけるような法理が果たして導き出されるのか、私としてははなはだ心許ないのである。
豊田氏の報告は、憲法9条とならんで「改憲」攻撃にさらされている憲法24条の男女平等原理の成立史に、クリティカルなまなざしを注ぐものだった。男女平等主義を謳う憲法24条は近代憲法を乗りこえた現代的・革新的性格をもつと評価され、ジェンダー法学の分野でもこの視点から24条護憲論が主流的見解となっている。しかし、豊田氏が明らかにしたように、帝国議会での審議過程から浮かび上がる憲法24条の男女平等主義のイメージは、実は、明治民法的な戸主権や「家」制度の否定にとどまるものでしかなかった。帝国議会において、両性の「本質的平等」という文言が「差別的平等」であり、「生理的、心理的」相違に基づく「合理的な差別」を認めるものとして理解されていたという豊田氏の指摘はきわめて重要である。結局この程度の男女平等原理にしか立脚していなかった日本国憲法下において、戦後日本社会において実際に形成されたのは、「稼ぎ手としての男子」と「家事・育児の担い手」としての女子という高度にジェンダー化された性別分業に基づく「近代家族」であり、その形成と維持を促進するような法体系であったと豊田氏は指摘する。
憲法24条のシロタ草案では盛り込まれていた非嫡出子差別の禁止が「詳細に過ぎる」という理由で他の具体的条文案とともに削除されたことも、現に非嫡出子相続分差別規定の最高裁合憲判決(1995年)が、憲法研究者や日本弁護士連合会の反対にもかかわらず定着している事実を鑑みれば、きわめて重い事実と言わなければならない。同様に、アメリカ合衆国をはじめとする海外諸国で、ゲイ・レズビアンの承認と権利の保護が就業差別の禁止や同性婚の法的保護の問題などをめぐって現実政治の争点となっている現状から見れば、明文で「両性の合意」を婚姻の前提として規定した24条のいわゆる「異性愛・異性婚主義」もまた批判の対象とならざるを得ないだろう。
憲法24条護憲論は、右からの「両性平等」攻撃に対して護憲を訴える一方で、非嫡出子差別や同性婚問題などに表れた24条の限界をめぐる批判に対しては、現行日本国憲法の発展的解釈により、婚外子差別の禁止やゲイの権利、同性婚の保護といった課題も十分に乗りこえることができる問題だとする立場が主流である(10)。憲法第3章の権利主体としての「国民」を判例・通説が外国人にも拡大適用してきたのと同様の発想であろう。しかし、現実には法律婚保護主義のもとに相続や無国籍児問題に見られるように婚外子差別は厳然として存在し、そうしたことが日本社会の少子高齢化の加速にも一役買っている。ゲイ・レズビアンの権利に関しても、明示的に「両性」を前提とする現行憲法下で、はたして同性婚を認めて異性婚と同様に法的に保護する制度が成立する余地があるのかは、きわめて疑問である。
日本国憲法の近代憲法的な限界を現代的な発展的解釈と判例の前進によって克服しようとするリベラル派憲法学の見解は、結局、護憲を前提とするがゆえに出てくる議論なのであろう。そこには「右」からの攻撃にさらされる9条や24条護憲の優先という政治的課題があり、いったん改憲に道を開けば、保守ポピュリズム的な方向でさまざまな反動的改憲が行われかねないという見通しがあるのだろう。そこに底流しているのは、憲法問題をめぐる政治不信(政治家は憲法改悪を提案してしまうに違いない)と国民不信(国民は国民投票で憲法改悪に賛成してしまうに違いない)である。改憲に前向きな世論調査のなかでも9条護憲派が「圧倒的」多数を占めている事実をふまえれば、このような護憲の憲法学は、憲法の番人を法曹が独占するエリート主義と批判されても仕方のない面もあるだろう。
改憲手続きが立法化されたからといってただちに改憲が実現するとは限らない。しかし、歴史家的タイムスパンで考えれば、長期的には国民投票をへて憲法が部分的に改正されることは不可避だと思われる。硬性憲法としての性格自体が変化する可能性も否定できない。そうなれば民主党が主張するように「解釈改憲」の余地が次第に狭まる一方で、9条に限らず、憲法条文と「現実」や「政策」を整合させようとする多様な要求が噴出することは避けられないだろう。平等原理や権利主体について、もっと具体的な社会集団を想定した明文化を求める運動も、多様な集団を担い手として展開することだろう。それらが複雑な政治力学をもたらして、改憲に向けた多数派形成をめざした政治が活性化してゆくことも避けられないだろう。
このような事態を喜ぶべきなのか、その不幸を嘆くべきなのかは議論が分かれるところである。文字通りのカッコなしの護憲によってのみ、日本国憲法の平和主義を守り、革新的マニフェストを実現することはできないと考える立場からすれば、日本国憲法の限界を批判して「創憲」・「加憲」や修正を求めることは、憲法「改悪」派に足下をすくわれかねない「護憲」勢力を分断する行為である。これに対して、たとえば環境権や外国人・非嫡出子差別の禁止や同性婚の保護などを明文化していない日本国憲法の現状は耐え難いと考える立場からすれば、憲法「改悪」を封殺するための護憲の論理は、日本国憲法をめぐるきわめて重要な問題について日本社会を判断停止の状態に置き、特定の地域、集団、環境を犠牲にしてきたことが批判されなければならないということになるだろう。私としては、これら犠牲にされてきた人々・ことどもが気になってしようがないというのが、一聴衆としての感想であった。
ジェンダー論から法の政治学を展開する岡野八代は、法主体の問題をめぐって私たちが「可能性として想像することさえ予め排除してきた生のあり方」への承認を迫ったゲイ・レズビアン運動が提起した問題として、「法の主体として普遍性を求めることは、そこに包摂し得ない残余を、そうした主体に対する『他者』として回帰させることになる」と述べている(11)。その意味において、同時代を批判的に読解することを使命とする同時代史学会が、護憲かカッコつきの「護憲」かの立場の違いを超えて、日本国憲法にクリティカルなまなざしを注ぎ、日本国憲法における『他者』発見の場となったことを私は喜びたいと思う。
(1) http://www.kenpoukaigi.gr.jp/seitoutou/20040610jiminkaikenPTronten2.htm
(2) 本稿では内容を問わず現行の日本国憲法を改めることをカッコなしの改憲と呼び、日本国憲法の平和主義と革新主義的性格を守るためには一切の改憲に応じるべきではないとする立場をカッコなしの護憲と呼ぶ。また、自民党・安倍政権流の憲法改悪をめざす立場をカッコつきの「改憲」、日本国憲法の平和主義と革新主義的性格を守り、さらにいっそうこれを発展させるためには一定の改憲を容認あるいは必要だと考える立場をカッコつきの「護憲」と呼ぶ。
(3) http://www.dpj.or.jp/manifesto04/9.html
(4) http://www.komei.or.jp/election/sangiin07/policy/jutenseisaku2007.pdf
(5) 渡辺治『増補 憲法「改正」──軍事大国化・構造改革から改憲へ』旬報社、2005年、43〜44頁。
(6)改憲に向けた世論を抽出しようとする傾向が見られる読売新聞社世論調査(面接式、2006年4月)においても、憲法9条については解釈・運用で対応する、厳密に解釈するとの両者を含めた改正不要論が53.5パーセントで、9条改正論の39.3パーセントを大きく上回っている。その一方、自衛隊は合憲とすべきだとする意見が71.2パーセントに達している。http://www.yomiuri.co.jp/feature/fe6100/koumoku/20060404.htm
外務省が行った世論調査(2002年)では、日本の平和と安全が守られている要因(複数回答可)で平和憲法が63.6パーセントで第1位、アメリカとの同盟関係が50.9パーセントで第2位であった。http://globalwarming.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/ah_chosa/ah_chosa.html#1-sq
(7)トーマス・マン著、関楠生訳『ファウスト博士』岩波文庫(上・下)、1974年。
(8)前掲・読売新聞世論調査参照。
(9)辻村みよ子『憲法(第2版)』日本評論社、2004年、158~159頁。
(10)中里見博『憲法24条プラス9条:なぜ男女平等がねらわれるのか』かもがわ出版、2005年、57~61頁。
(11) 岡野八代「『承認の政治』に賭けられているもの」『法社会学』64号(2006年)、72頁。


Recent Comments